「2035年、子どもたちはどんな社会を生きているだろう?」
そんな未来への問いから始まった、白梅学園大学での連続授業「子どもデジタル論(STEAM教育)」。
2025年4月〜6月にかけて、全8回にわたる授業を、NPO法人Pendemyデジタル教育ラボのメンバー3名が担当させていただきました!
授業構成とねらい
保育・教育・福祉など、子どもに関わる分野を目指す学生たちに向けて、全8回で“STEAM教育”の考え方を体験しながら学べるよう、構成しました!
前半(1〜4回)|未来と教育をつなげる
まずは「未来を生きる子どもたちに、どんな力が必要か?」を考えるところからスタート。
AIやメタバース、自動運転など、2035年の未来予想をベースに、
今の教育に足りない視点や、STEAMの役割についてディスカッションしました。
そこから、遊びや絵本の中にあるSTEAMの要素を探すワークにも挑戦。
“難しい”と思われがちなSTEAM教育が、日々の保育・福祉の現場でも実践できることを体感してもらいました。
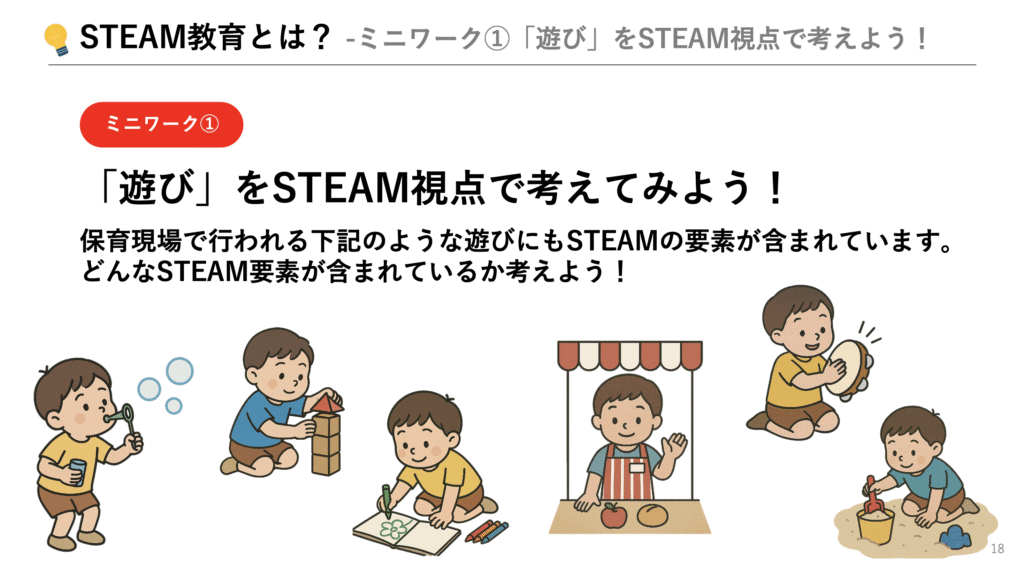
中盤(5〜6回)|STEAMを体験する
実際にSTEAMの授業を子ども向けにやってみるなら?という視点で、Pendemyでも人気の「デジタル音楽祭」ワークショップを実際に体験。
紙コップでギターをつくって音の仕組みを学び、アプリで音を重ねて音楽をつくる…
学生たちは大人になって久しぶりに“夢中で手を動かす時間”を楽しんでくれました。
さらに、フリースクールを想定したSTEAM教育ワークショップの企画にも挑戦!
“どんな子どもでも楽しめるSTEAM体験って?”をチームで考え、アイデアを出し合いました。

後半(7〜8回)|自分たちで「届ける」力を
最終回では、グループで考えたワークショップを実際に発表。
Canvaでスライドをつくり、見せ方や問いかけの工夫まで、みんなで試行錯誤。
発表後は、お互いの企画にフィードバックし合いながら、「学びをデザインする力」や「伝える力」も育んでいきました。

授業を担当したメンバー

木村 隼人(Pendemy代表理事)

向山 佳歩

西野 はる菜
おわりに|子どもに届けたい“問いから始まる学び”
STEAM教育は、理数系の力だけでなく、“子どもの好奇心に寄りそう力”でもあります。
「これってなんでだろう?」から始まる探究のプロセスを、学生たち自身が楽しみながら学べた8回でした。
この授業で生まれた“問い”と“ひらめき”が、未来の保育・福祉・教育現場につながっていくことを願っています。








